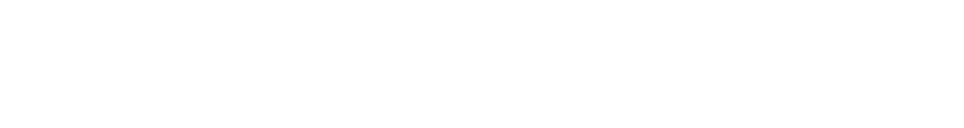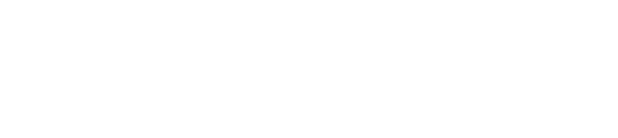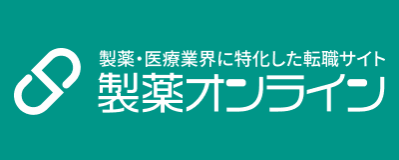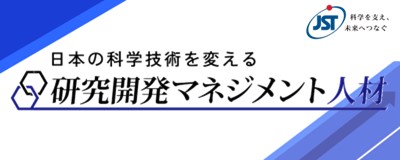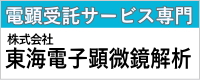バイオテクノロジーセミナー・
バイテクショートセミナー・
ナイトカフェセミナー
バイオテクノロジーセミナー
13:00-13:50 第3会場(302)
- タンパク質ダイナミクスを解き明かす NanoLuc®の“見つけるチカラ”
共催:プロメガ株式会社 - 司会
酒井 厚(プロメガ株式会社) - 講演者
稲川 悠紀(プロメガ株式会社) -
みどころ
分子量が小さく非常に明るい NanoLuc® ルシフェラーゼが発表されてから10年以上が経ち、多くのアプリケーションが開発されました。低発現のプロモーターでも検出可能なレポーターアッセイ、分子間相互作用を研究するためのNanoBRET®やNanoLuc® Binary Technology (NanoBiT)、 免疫測定系を革新するLumit®と、NanoLuc®は細胞内の遺伝子応答とタンパク質ダイナミクスを生理学的に妥当なレベルで研究するための基盤となっています。本セミナー前半では、NanoLuc® 技術を体系的に俯瞰し、それぞれの特徴と利点を整理します。続いて、創薬分野で注目されるGPCR研究への応用事例を取り上げ、受容体シグナル伝達解析やスクリーニングへの具体的な活用法をご紹介します。最後に、NanoLuc®技術を活用した新しい挑戦的な研究を後押しする、アカデミアやベンチャーの皆様向けの支援プログラムをご案内します。NanoLuc®技術の可能性と、未来の研究を支えるサポート体制に是非ご注目ください。
13:00-13:50 第4会場(303)
- 細胞空間解析の最前線:マルチプレックスイメージングと画像解析による統合的理解
共催:ライカマイクロシステムズ株式会社 - 司会
田中 晋太郎(ライカマイクロシステムズ株式会社) - 講演者
単一細胞時空間イメージングが解き明かす転写ダイナミクスの制御機構
大石 裕晃(九州大学 生体防御医学研究所 高深度オミクスサイエンスセンター) - 講演者
撮る速さが“分かる”を加速する:THUNDER × AIVIA
鶴巻 宣秀(ライカマイクロシステムズ株式会社) -
みどころ
本セミナーでは、大石裕晃先生(九州大学 生体防御医学研究所 高深度オミクスサイエンスセンター)をお迎えし、単一細胞レベルでの転写動態制御に関する最先端の研究をご紹介いただきます。遺伝子の転写は、活性状態と不活性状態の間を確率的に遷移する動的過程であり、その制御機構の解明には単一細胞レベルでの解析が不可欠です。大石先生のご研究では、蛍光イメージング技術を駆使し、ライブイメージングによる転写の時間的動態の解析に加え、空間オミクスを用いて核内構造との空間的関係を明らかにされています。
本講演では、生細胞内で転写活性と対応する遺伝子座を同時に可視化する独自の手法によって明らかとなった制御機構、さらに逐次蛍光イメージングに基づく空間マルチオミクス解析から見出された新たな転写制御様式についてご紹介いただきます。加えて、これらの高度なイメージング技術と顕微鏡システムを基盤とした転写操作技術についてもご解説いただきます。
またライカマイクロシステムズからは、実際のアプリケーション例を交えながら、撮影速度とAI解析技術の融合が生命科学研究における「分かる」をどのように加速するかをご紹介します。THUNDERは高速・高精度なイメージングを可能にし、AIVIAはその膨大な画像データを迅速かつ正確に解析します。これらの技術を組み合わせることで、細胞や組織の大量なデータから、研究者がより深い洞察を得ることが可能になります。
13:00-13:50 第15会場(501)
- マルチオミクスを駆動するイルミナ新技術とプロテオームバイオマーカー探索
共催:イルミナ株式会社 - 司会
藤原 鈴子(イルミナ株式会社) - 講演者
Illumina イノベーションロードマップ
仲 健太(イルミナ株式会社) - 講演者
プロテオームプラットフォーム間検証および疾患バイオマーカー探索
松田 浩一(東京大学) -
みどころ
イルミナはマルチオミクス解析を推進する様々なテクノロジーの製品化を進めています。 本セミナーでは、これら次世代テクノロジーの概要についてご紹介するとともに、東京大学大学院新領域創成科学研究科/バイオバンク・ジャパン代表の松田浩一先生をお招きし、 『プロテオームプラットフォーム間検証および疾患バイオマーカー探索』についてご講演賜ります。
ご講演要旨:近年、ゲノム創薬などを目的としてProteome解析、メタボローム解析が広く実施され、海外ではUKバイオバンクなどで50万人規模の解析が進んでいる。Proteome解析には、RNA aptamerとarrayテクノロジーを用いたSomascan、PEA法に基づくOlinkHTが製品化され、大規模解析などに広く活用されている。さらにイルミナ社よりRNA aptamerに付加したバーコード配列に基づく新しいProteomeシステム(Illumina Protein Prep, IPP)が開発されている。我々は、プラットフォーム間の比較検討のために、市販前のIPPのプロトタイプ、Olink HT、およびSomascanシステムを75例の同一血漿検体を用いて解析した。比較検証結果を本セミナーでは紹介するとともに、がんおよびその基礎疾患を対象として、バイオバンク・ジャパンの検体を用いて進めている疾患バイオマーカー探索の成果についてお示しする。
13:00-13:50 第16会場(502)
- 超解像ライブイメージングで探る多細胞動態のメカニズム
ー分子の協奏が紡ぐ生き物のかたちづくりー
共催:カールツァイス株式会社 - 座長
西村 聡文(カールツァイス(株)) - 講演者
超解像ライブイメージングで探る多細胞動態のメカニズム
ー分子の協奏が紡ぐ生き物のかたちづくりー
倉永 英里奈(京都大学大学院薬学研究科 組織形成動力学分野) - 講演者
新型マルチモーダル共焦点レーザ顕微鏡 LSM 990のご紹介
ー最新型ワイドフィールド三次元技術と融合した革新的共焦点レーザ顕微鏡ー
佐藤 康彦(カールツァイス(株)) -
みどころ
発生過程における形態形成は、個々の細胞の運動と、それを支える分子動態の協調によって実現します。本講演では、ショウジョウバエ蛹の体の中で視られる集団的な細胞移動を対象に、超解像ライブイメージングを用いてそのダイナミクスを可視化・解析した研究を紹介します。分子スケールから多細胞スケールへと連なる協奏的な動きを追うことで、細胞がどのように協調して動き、生き物のかたちをつくるのかという問いに、「視る」ことから迫ります。
Zeissからは、3Dイメージングの常識を変える Lightfield 4D、最新の超解像イメージング、13色以上の超多色イメージングそして分子動態解析と豊富なソリューションを兼ね備えた新型共焦点顕微鏡LSM990をご紹介致します。
13:00-13:50 第17会場(503)
- 修飾特異的細胞内抗体の開発とその利用
共催:株式会社モノクローナル抗体研究所 - 講演者
修飾特異的細胞内抗体の開発とその利用
木村 宏(東京科学大学) -
みどころ
遺伝子コード型の細胞内抗体は、内在性タンパク質の可視化や操作に有用ですが、多くの一本鎖抗体は折り畳みや安定性に問題があるため、開発は簡単ではありませんした。しかし、最近のAIを用いたタンパク質デザインにより、安定性を向上させることが可能となり、細胞内抗体の開発を効率よく行うことが可能になってきました。本セミナーでは、ヒストンなどの翻訳後修飾を認識する細胞内抗体の開発とその利用について紹介します。
13:00-13:50 第3会場(302)
- 次世代シーケンサーを用いた疾患遺伝子の探索法について
共催:ニュー・イングランド・バイオラボ・ジャパン株式会社 - 座長
吉田 直樹(ニュー・イングランド・バイオラボ・ジャパン株式会社) - 講演者
次世代シーケンサーを用いた疾患遺伝子の探索法について
水上 洋一(山口大学大学研究推進機構 遺伝子実験施設) -
みどころ
次世代シーケンス(NGS)は、従来のサンガー法と比較して高スループットかつ高速で、低コスト化が進んだ革新的な解析技術です。全ゲノム解析、エクソーム解析、RNA-seq、ChIP-seq、ATAC-seq、Bisulfite-seq、メタゲノム解析、特定遺伝子パネルのターゲットシーケンスなど、多様な応用範囲を持ちます。一方で、NGSはいくつかの問題もあります。1回のランで膨大なデータが発生し、高額な計算コストが必要になります。データ品質と精度(GCバイアスやインデル率など)やサンプル汚染、PCRバイアスでの偽陽性・偽陰性の発生、リファレンスやデータベースの不完全性さや構造変異・CNV・エピジェネティック修飾などの解析の難しさが残されています。
このセミナーでは、全ゲノム解析やRNA-seq解析を中心にデータの精度を改善するためのサンプルの前処理や解析の選択方法をご説明します。また、様々な疾患の事例を用いて空間トランスクリプトーム解析やゲノム編集技術と組み合わせたNGS解析データの検証結果をご紹介します。
13:00-13:50 第4会場(303)
- シングルセルデータを空間データへーTrekker技術が開く生命科学の新たな時代に
共催:タカラバイオ株式会社 - 講演者
浅井 雄一郎(タカラバイオ株式会社) - 講演者
シングルセルデータを空間データへーTrekker技術が開く生命科学の新たな時代に
安益 公一郎(タカラバイオ株式会社) -
みどころ
タカラバイオは分子生物学研究試薬とゲノム解析サービスのフロンティア企業として、微量検体のゲノム・トランスクリプトームにおける次世代シーケンス(NGS)解析分野に注力し、近年ではシングルセル解析分野で研究ソリューションを提供してきました。本セミナーでは、シングルセル解析や空間解析の基本コンセプトから技術の進化をたどりながら、位置情報を持つDNAバーコードで細胞核をタグ付けするこれまでにないユニークな〝Trekker技術“を利用した真の空間トランスクリプトーム解析用試薬と解析サービスをご紹介します。
13:00-13:50 第5会場(304)
- ProteoAnalyzerによるサンプルQCが支える質の高いプロテオーム解析
共催:アジレント・テクノロジー株式会社 - 司会
尾崎 正和(アジレント・テクノロジー株式会社) - 講演者
ProteoAnalyzerによるサンプルQCが支える質の高いプロテオーム解析
川島 祐介(かずさDNA研究所 ゲノム事業推進部 応用プロテオミクスグループ) - 講演者
より効率的なタンパク質解析を実現するアジレント製品のご紹介
津本 裕子(アジレント・テクノロジー株式会社) -
みどころ
サンプル品質のばらつきは、プロテオーム解析における再現性を大きく左右する重要な要因です。特に臨床検体や貴重な研究材料では、前処理や測定の段階で生じるわずかな差異が、最終的な解析結果に大きな影響を及ぼすことがあります。しかしながら、従来のプロテオーム解析におけるサンプルQCは、タンパク質定量による総量の確認にとどまっているのが現状です。本セミナーでは、SDS-PAGEのようにタンパク質の分子量プロファイリングを取得でき、さらにシグナル強度から定量値を算出できるProteoAnalyzer を用いた、サンプルQCを起点とする解析ワークフローの利点をご紹介します。あわせて、このQCを基盤として展開している弊所の質の高いプロテオーム解析についてもご説明します。
13:00-13:50 第9会場(411+412)
- 博士号取得者の多様なキャリア形成を考える
共催:一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン(LINK-J) - モデレーター兼パネリスト
橋本 遥(株式会社Convallaria) - 講演者
香月 康宏(鳥取大学 染色体工学研究センター) - 講演者
木下 美妃(ANRI株式会社) - 講演者
栗原 志夫(株式会社AGRI SMILE) - 講演者
戸田 裕之(ノバルティス ファーマ株式会社 インターナショナルユニットジャパン メディカル・アフェアーズ本部) -
みどころ
バイオ・ライフサイエンス分野やアグリ分野において、研究成果を社会に還元するためのキャリアの多様化が進んでいます。博士号取得者が企業やスタートアップで活躍する姿は、産学連携の新たな可能性を示しています。
本企画では、アカデミア以外の道を選び、研究者としての知見を活かして社会に貢献している先輩たちをお招きし、キャリア形成のリアルを語っていただきます。企業研究者、スタートアップ起業者、異業種への転向など、多様なロールモデルを通じて、若手研究者が自身の未来を描くヒントを得られる場を提供します。
分子生物学会キャリアパス委員会との連携により、研究と社会をつなぐキャリア支援のあり方を考えます。
各登壇者の所属先URL
株式会社Convallaria https://convallaria.co.jp/
鳥取大学 染色体工学研究センター https://www.med.tottori-u.ac.jp/lifesciences/research/staff_kazuki.html
ANRI株式会社 https://anri.vc/ja
株式会社AGRI SMILE https://agri-smile.com/
13:00-13:50 第15会場(501)
- 透明化と多色イメージングが拓く動的コネクトーム研究
共催:株式会社エビデント - 司会
今井 雄一郎(株式会社エビデント) - 講演者
研究を加速する進化した共焦点イメージング ー高速、高効率、高画質への挑戦ー
香西 直樹(株式会社エビデント) - 講演者
透明化と多色イメージングが拓く動的コネクトーム研究
今井 猛(九州大学大学院医学研究院) -
みどころ
脳機能は脳内の多様な細胞によって構成される巨大なネットワークが動的に変化することで発現する。我々は、動的コネクトームを捉えるため、蛍光顕微鏡を使って脳の機能やネットワーク構造を探るための透明化技術や、多色標識・イメージング技術の開発に取り組んできた。本口演では、固定標本を高解像度観察するための透明化液SeeDB2や、生きた生体組織を非侵襲的に深部観察するための透明化液SeeDB-Live、神経回路のマルチプレックス解析を実現する蛍光バーコード法について紹介する。また、こうした技術を実現する上で重要な顕微鏡技術やその取り扱い方法についても解説する。
13:00-13:50 第16会場(502)
- 「あなたの科研費研究を最先端の技術で支援します」
生命科学 4 プラットフォームによる最先端技術支援説明会
共催:文部科学省 学術変革領域研究 学術研究支援基盤形成 生命科学連携推進協議会 - 座長
武川 睦寛(東京大学 医科学研究所) - 講演者
生命科学連携推進協議会の活動紹介
武川 睦寛(東京大学 医科学研究所) - 講演者
先端モデル動物支援プラットフォームの支援活動紹介
清宮 啓之(がん研究会) - 講演者
先進ゲノム解析研究推進プラットフォームの支援活動紹介
黒川 顕(国立遺伝学研究所) - 講演者
コホート・生体試料支援プラットフォームの支援活動紹介
醍醐 弥太郎(東京大学 医科学研究所) - 講演者
先端バイオイメージング支援プラットフォームの支援活動紹介
三浦 正幸・真野 昌二(基礎生物学研究所) -
みどころ
生命科学4プラットフォームでは、文部科学省のご支援の下、先進的技術支援・リソース提供・技術相談などを通して、科研費による生命科学研究を最先端で支援しています。本セミナーでは、各プラットフォームの研究支援内容や申請方法、これまでの研究成果について詳しく紹介します。科研費で実施している全ての生命科学研究が支援対象となり得ますので、この機会を通じて、さらに多くの研究者の皆様に当支援活動を知っていただき、研究活動にお役立ていただけましたら幸いです。
13:00-13:50 第17会場(503)
- がん進行を捉える高精度空間オミクス
共催:横河電機株式会社 - 座長
松井 等(横河電機株式会社) - 講演者
がん進行を捉える高精度空間オミクス
大川 恭行・富松航佑(九州大学 生体防御医学研究所) -
みどころ
がんを含む様々な疾患で効果的な治療戦略を立てるため、患者一人ひとりに合わせた「個別化医療」の重要性が高まっています。しかし従来の個別化医療では、大規模データに基づく既知の診断マーカーや治療実績が必要で、新しい症例や未知の病態、希少疾患には対応が困難でした。そのため、個々の患者の組織で生じる異常な細胞やその周辺環境、さらには原因となる分子を直接検出・解析できる手法の開発が求められていました。しかし、これまでの技術では組織内に生じる細胞間シグナル伝達活性化と細胞状態の関係を十分な解像度で捉えることはできませんでした 。この課題に対し私たちは新たな抗体「Precise Emission Canceling Antibody(PECAb)」を開発しました。PECAbを用いることで蛍光免疫染色シグナルを染色後に消光し、同一試料で染色を繰り返す多重染色が実現しました。これにより、細胞の空間的な配置情報を保ったまま、シグナル伝達分子を含む最大206種類ものタンパク質の発現を同一組織内で同時に検出する世界最高レベルの「空間オミクス」解析系を確立しています 。※なお、この抗体名「PECAb」は、染色したシグナルを隠したり現したりできることから、英語の幼児遊び「いないいないばあ(Peek-a-boo)」に由来しています。
得られた膨大なデータを解析することで、組織内の個々の細胞が示す状態変化を疑似時間軸上で再構築し、様々なシグナル伝達経路の活性化ダイナミクスを推定することに世界で初めて成功しました 。さらにこの技術を実際のがん患者検体に適用した結果、がん細胞が転移能を獲得する過程にある中間状態を捉え、その状態を引き起こすシグナル伝達分子を個別の患者レベルで検出することにも成功しました 。これは転移へと向かうがん細胞の道筋を明らかにする画期的成果であり、将来的には患者ごとに最適な治療標的(治療介入ポイント)を見つけ出す手法として応用できる可能性があります 。本研究の成果と研究開発状況について講演します。
13:00-13:50 第3会場(302)
- 分子から細胞は創れるか?合成生物学が挑む人工細胞のフロンティア
共催:ツイストバイオサイエンス - 司会
野口 匡則(ツイストバイオサイエンス) - 講演者
自分で自分を作る(増殖する)分子システムの実現に向けて現状と課題
市橋 伯一(東京大学大学院総合文化研究科) - 講演者
Writing the Future 多様な遺伝子設計を支えるTwist合成DNAツール
須藤 倫子(ツイストバイオサイエンス) -
みどころ
近年、生命科学の最大の問いの一つである「分子から細胞を創れるか?」という挑戦が加速しています。本セミナーでは、自己複製・増殖が可能な分子システムや人工細胞の構築を目指す最先端の研究に迫ります。生命の根幹機能であるDNA複製、転写、翻訳を試験管内で再構成し、最小限の因子だけで自己増殖するシステムをどのように実現しようとしているか、この分野の第一線で活躍する市橋伯一教授による最先端の事例と、遺伝子設計を支えるTwist Bioscienceの合成DNAツールをあわせてご紹介します。
13:00-13:50 第15会場(501)
- クライオ光学顕微鏡:細胞の動きを「止めて」観る
共催:株式会社ニコンソリューションズ - 司会
鶴旨 篤司(株式会社ニコンソリューションズ) - 講演者
クライオ光学顕微鏡:細胞の動きを「止めて」観る
藤田 克昌(大阪大学大学院 工学研究科) -
みどころ
従来の顕微鏡技術では、空間分解能や時間分解能、信号強度の制約から、細胞内で起こる一瞬の現象を鮮明に観察することは困難でした。本講演では、顕微鏡観察中に細胞をごく短時間で急速凍結し、その瞬間の状態を固定したまま高解像度・高感度に観察できる「クライオ光学顕微鏡」を紹介します。本技術により、分子の分布や状態を保持したまま瞬間的なふるまいを可視化でき、かつ光損傷を抑えて微弱なシグナルも検出可能です。細胞ダイナミクスや分子生物学研究に新しいアプローチを提供します。
バイテクショートセミナー
13:20-13:50 セミナー会場1
- 高精度細胞イメージング評価を実現するマイクロプレートのご紹介
共催:日本ゼオン株式会社 - 講演者
高精度細胞イメージング評価を実現するマイクロプレートのご紹介
石神 朋広(日本ゼオン株式会社) -
みどころ
In vitro薬剤スクリーニングにおいては、ヒトiPSC由来分化細胞をはじめ、がん細胞株、初代細胞、不死化細胞株など、さまざまなヒト細胞モデルが活用されており、動物実験の代替手法として期待されています。これらの細胞モデルを用いた薬剤評価においては、細胞、培養プレート、評価機器などを組み合わせた、生理学的に適切かつ包括的なモデル・アッセイ系の構築が進められています。本セミナーでは、鮮明な画像を短時間で取得可能にする細胞培養プレート (シクロオレフィンポリマー製マイクロプレート) を用いて培養した細胞のハイコンテントアナリシス機器 (共焦点イメージングサイトメーター等) による細胞観察結果と、各種アッセイ事例をご紹介させていただきます。
13:20-13:50 セミナー会場2
- CST® InTraSeq™技術による新たなシングルセル解析の知見
共催:セルシグナリングテクノロジージャパン株式会社 - 講演者
CST® InTraSeq™技術による新たなシングルセル解析の知見
阿部 晋也(セルシグナリングテクノロジージャパン株式会社) -
みどころ
InTraSeq (Intracellular Protein and Transcriptomic Sequencing) は、たった1回の実験で、疾患の発症に関わるシグナル伝達経路の特定や分子メカニズムの解明を可能にする新たな技術です。この技術は、数千個の細胞におけるRNA量だけでなく、細胞内および細胞表面の両方のタンパク質を同時検出できるため、シングルセルレベルのトランスクリプトームを用いたシグナル伝達経路の解析が可能です。本セミナーでは、Cell Signaling Technology (CST) が開発および検証したInTraSeq 3’技術について、その仕組みと利点をご紹介します。
13:20-13:50 セミナー会場3
- 「研究者の新たなキャリアの選択肢 〜スタートアップで実現する研究と社会の橋渡し〜」
共催:Craif株式会社 - 座長・司会
市川 裕樹(名古屋大学 未来社会創造機構 / Craif株式会社) - 講演者
「研究者の新たなキャリアの選択肢 〜スタートアップで実現する研究と社会の橋渡し〜」
水沼 未雅・ハヴェルカ ミロシュ・安東 頼子(Craif株式会社) -
みどころ
Craifは、尿中マイクロRNAをAIで解析する独自技術を強みに、がんの早期発見・予防という世界的課題に挑戦しています。50以上の共同研究を基盤に臨床開発や社会実装を進め、米国でのFDA申請を見据えた国際展開にも踏み出しています。
本セミナーでは、Craifの研究を牽引する異なるバックグラウンドを持つ3名が登壇。研究者がスタートアップで果たせる役割や必要なスキル、アカデミアや大企業との違い、そして研究成果を社会実装へとつなげるプロセスについて議論します。
「アカデミアに進むか、就職をするかで迷っている」「スタートアップで研究をするってどういう感じなんだろう」――そんなキャリアの悩みに応えるセッションです。研究の枠を超えてキャリアを広げたい方に、新たな視点や“自分らしいキャリアの可能性”を見つけるきっかけをお届けします。
13:20-13:50 セミナー会場1
- PCR産物から細胞内タンパク質まで - 高精度な解析を実現する新アプローチ
共催:GENEWIZ™ (アゼンタ株式会社) - 司会
岡崎 泰典(GENEWIZ(アゼンタ株式会社)) - 講演者
PCR産物の新しい配列解析ソリューション
矢吹 崇吏(GENEWIZ(アゼンタ株式会社)) - 講演者
細胞内タンパク質をターゲットとするシングルセルタンパク質解析(CITE-Seq)
秋山 康一(GENEWIZ(アゼンタ株式会社)) -
みどころ
本セミナーでは、GENEWIZの新技術であるPCR-EZおよびCITE-Seqを用いたシングルセル解析をご紹介します。
PCR-EZは、ONT社のシーケンサーを活用したロングリードNGSベースのPCRシーケンシングサービスです。精製済みまたは未精製のPCR産物を最大25kbまで迅速にシーケンシング可能です。従来のサンガーシーケンシングでは約1,000bpまでが解析の限界ですが、PCR-EZはハイスループットかつ短納期で、より長く包括的なシーケンシングデータを提供します。本セミナーではサンプル提出の方法や納品物の内容についてもご紹介します。
また、CITE-Seqを用いたシングルセル解析技術により、細胞膜表面だけでなく細胞質内のタンパク質も解析可能となりました。当社は複数のプロトコールに対応しており、実例紹介とともに必要なサンプル条件についても解説します。
13:20-13:50 セミナー会場2
- Biomek i7による single-cell RNA-seq/T細胞受容体解析のライブラリ調整自動化の実際とT細胞のCOVID-19ワクチン応答解析への応用
共催:ベックマン・コールター株式会社 - 司会
小野寺 純(ベックマン・コールター株式会社) - 講演者
Biomek i7による single-cell RNA-seq/T細胞受容体解析のライブラリ調整自動化の実際とT細胞のCOVID-19ワクチン応答解析への応用
七野 成之(東京理科大学 生命医科学研究所) -
みどころ
次世代シーケンサー(NGS)を用いた網羅的遺伝子発現解析は、single-cell RNA-seq (scRNA-seq)を始めとして高度化・多検体化・高価格化の傾向にあり、大規模な解析の実施や幅広い解析支援を行う上で、NGSライブラリ調整の自動化は実験失敗リスクの低減やスループット向上の観点から重要である。Biomek i7は液体の分注のみならず、NGSライブラリ調整に必要な機器や環境との接続、高密度なデッキポジション数、柔軟なプログラム設計機能によりNGSライブラリ調整工程大半の自動化が可能である。当教室では独自に開発したscRNA-seqやT細胞受容体解析(TCR-seq)の自動化をbiomek i7で実装し、解析支援を産学問わず広く提供してきた。本講演では、Biomek i7によるscRNA-seq/TCR-seqライブラリ調整自動化の実装の実際とそのtips、またそれを活用したCOVID-19ワクチンに対するT細胞応答解析への応用例について紹介したい。
13:20-13:50 セミナー会場3
- ドロップレットデジタルPCRの新展開
共催:バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社 - 講演者
ドロップレットデジタルPCRの新展開
八田 幸憲(バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社) -
みどころ
ドロップレットデジタルPCR (ddPCR)は、絶対定量と高感度検出を可能にする第3世代PCR技術として、依然、注目される技術の1つです。 本セミナーでは、ddPCR技術の最新動向と、分子生物学研究における革新的アプリケーションをご紹介します。ddPCR技術の進歩により実現された高精度定量解析の可能性と、実践的活用法について詳しく解説いたします。
13:20-13:50 セミナー会場4
- 電気泳動の最前線 MultiNAⅡで何ができるのか
共催:株式会社島津製作所 - 司会
熊谷 英郷(株式会社島津製作所) - 講演者
電気泳動の最前線 MultiNAⅡで何ができるのか
曽我部 有司(株式会社島津製作所) -
みどころ
アガロースゲル電気泳動はジェノタイピングやゲノム編集など様々な分野で活用されている手法です。島津製作所ではマイクロチップ電気泳動装置MultiNAにより「電気泳動をもっと手軽かつ安全に、精度良く行いたい」というお客様の要望を叶えてまいりました。昨年リニューアルしたMultiNAⅡではDNA/RNAの有無やサイズを迅速かつ簡単に低コストで確認でき、自動分析フローによって業務の効率化が格段に進みます。本ショートセミナーではMultiNAⅡの豊富な機能とさまざまな活用事例を紹介します。
13:20-13:50 セミナー会場1
- GENE to Antibody – 高精度NGSで実現するハイブリドーマ解析とリコンビナント抗体作製
共催:GENEWIZ™ (アゼンタ株式会社) - 司会
岡崎 泰典(GENEWIZ(アゼンタ株式会社)) - 講演者
NGSによるハイスループット・高精度ハイブリドーマ解析
秋山 康一(GENEWIZ(アゼンタ株式会社)) - 講演者
End-to-Endで実現するリコンビナント抗体作製の最前線
矢吹 崇吏(GENEWIZ(アゼンタ株式会社)) -
みどころ
GENEWIZでは、抗体配列の取得からリコンビナント抗体作製まで、ワンストップで技術支援を行い、抗体研究開発の効率化をサポートします。特に、NGS技術を活用したハイブリドーマ解析サービスにより、混在する抗体遺伝子の可変領域を高精度に特定することが可能です。これにより、高感度・高解像度・ハイスループットで網羅的な抗体情報を取得できます。
また、“Gene-to-Antibody”のコンセプトに基づき、高品質なリコンビナント抗体を最短3週間で作製可能です。プロジェクトは要件に応じてカスタマイズでき、多様な抗体フォーマットへの対応実績があります。加えて、抗体専門家による技術サポートも提供しており、AI設計による抗体配列の機能性評価、抗体エンジニアリングによる物性改善、候補抗体のスクリーニングなど、幅広い開発プロセスに対応可能です。
本セミナーでは、これらの技術とサービスを活用した抗体探索から開発までの具体的な事例やプロセスをご紹介します。
13:20-13:50 セミナー会場2
- 信頼のIHCデータを生み出す鍵:再現性の課題を克服する抗体検証のすべて
共催:セルシグナリングテクノロジージャパン株式会社 - 講演者
信頼のIHCデータを生み出す鍵:再現性の課題を克服する抗体検証のすべて
阿部 晋也(セルシグナリングテクノロジージャパン株式会社) -
みどころ
免疫組織化学染色(IHC)は、組織内タンパク質解析に不可欠な手法ですが、実験の再現性確保が大きな課題です。この課題の多くは、使用する抗体の品質に起因します。本セミナーでは、IHCの再現性を高めるための鍵となる「抗体検証」について、その重要性と詳細なプロセスを解説します。Cell Signaling Technology (CST) が実践する多角的な検証プロセスに基づき、組織アレイや細胞ペレットを用いた特異性確認、ロットごとの品質管理など、信頼性の高いデータを得るための具体的なステップをご紹介します。本セミナーを通じて、皆様がより良い抗体選びができるようになり、それが研究成果の質の向上に繋がるようサポートいたします。
ナイトカフェセミナー
19:15-20:15 セミナー会場1
- Promega Dynamic Connection
共催:株式会社プロメガ -
みどころ
プロメガは、ナイトカフェセミナーにて「Promega Dynamic Connection」と題した特別イベントを開催いたします。本イベントは、プロメガ製品をご活用いただいている研究者の皆さまの交流を促進し、学術的なつながりを深めることを目的とした催しです。当日は、プロメガにゆかりのある方々をお招きし、和やかな雰囲気の中でネットワーキングを楽しんでいただける内容を予定しております。日頃の研究活動を支える製品を提供する企業として、研究者の皆さま同士の“ダイナミックなつながり”をお手伝いできることを願っております。
研究者同士の新たなつながりを見つけたい方、同じ製品を使っている仲間と交流したい方、ぜひご参加ください。詳細、参加申込につきましてはプロメガクラブメールマガジンで随時ご案内してまいります。
プロメガクラブ www.promega.co.jp/special/club/
19:15-20:15 セミナー会場1
- 特別パネルディスカッション「プロテーム解析のそこんとこ」 ~結局どれがいいの?~
共催:フォーネスライフ株式会社 -
みどころ
プロテオーム解析技術のそこんとこ、とことん話し合います。
プロテオーム解析は、アプタマーベース、抗体ベース、質量分析などがあります。近年では技術進歩に伴い、数千〜1 万程度のタンパク質を同時にプロファイリングできるようになってきており、ようやく「プロテオーム」と呼ぶにふさわしい網羅性を備えてきています。それぞれの技術には、一長一短ありますが、情報が分散している状況です。
そこで、実際の利用者によるパネルディスカッションを通して、それぞれの特徴、弱点なども含め、フラットなディスカッションを行い、知見を共有いただくことで、よりよいプロテーム解析のためのヒントを得ていただければと思います。