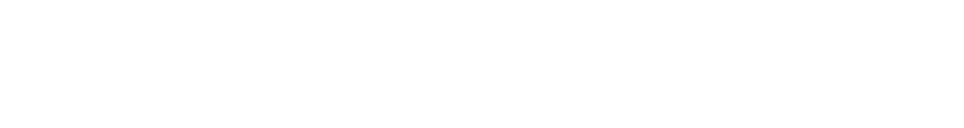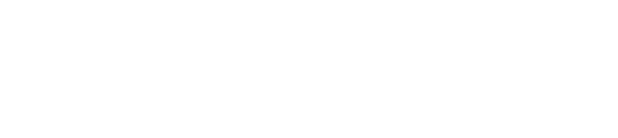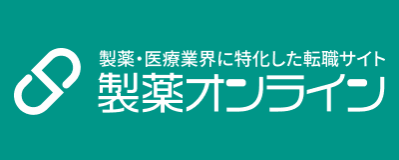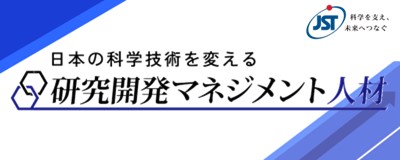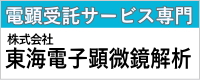マッチングイベント企画
このゆび、とーまれっ“Let’s gather here, in Yokohama!”
申込期間:
10月15日(水)~11月6日(木)17:00まで 締め切りました
お気軽にご参加ください♪
マッチングイベント企画とは?
第48回年会では“新しい出会い”をテーマにした交流イベントを開催いたします。
同じ目標に向かって努力されている方や、似た課題を抱えている方と出会い、語り合うことで、新しいつながりが生まれる ――そんな場となることを目指しています。
8,000名を超える参加者が集まる日本分子生物学会年会ならではの出会いもきっとあるはずです。
皆さまのご参加をお待ちしております!
開催概要
開催日時
12月3日(水)19:15~20:30
12月4日(木)19:15~20:30
※一部昼帯での開催あり
開催場所
パシフィコ横浜 ポスター展示会場内 特設スペース
※一部会議場での開催あり
★飲食の提供について
イベント開催中は、年会にてご用意した軽食、アルコール類、ソフトドリンク、さらに福井県の日本酒などをお楽しみいただけます。
飲食を交えながら、リラックスした雰囲気の中で交流を深めていただければ幸いです。


※本企画は初めての試みとなるため、応募状況により開催形式を変更させていただく場合がございます。
最新の情報は随時、本サイトにてご案内いたします。
事前参加申込方法
下記の申込フォームより、締切期日までに下記の必要情報をご登録ください。
事前参加申込をされた方は、優先的にご参加いただけます。
イベント当日は、事前参加申込をされていない方の飛び入り参加も受け入れる予定をしておりますが、参加希望者が多数になる場合は入場を制限する場合がございますので、優先的にご参加いただける事前参加申込をおすすめいたします。
- 申込期間:
- 2025年11月6日(木)17:00まで
- 参加資格:
- 年会にご参加予定の皆様 ※本イベントの参加には、年会の参加登録が必須です。
- 開催企画:
- 下記のリストをご参照のうえ、ご希望の企画をお選びください。
〈お申込に際して〉
・事前参加申込上限:1日当たり1企画まで
・当日は途中入退場および他の企画にもご参加いただけます。
・お申し込み状況によって、日程変更または中止になる可能性もございます。
・お申込みされた企画の詳細については、11月中旬ごろにメールまたは年会ホームぺージにてご案内を予定しております。
※一部、オーガナイザーよりご案内が届く場合もございます。
開催予定の企画一覧
当日案内ページをご参照ください。
当日の参加方法について
11月中旬ごろにメールまたは年会ホームページにてご案内いたします。
お問合せ先
第48回日本分子生物学会年会事務局(㈱エー・イー企画 内)
〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-4-4一ツ橋別館4階
Tel: 03-3230-2744
E-mail: mbsj2025@aeplan.co.jp